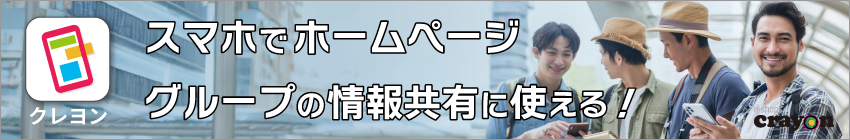「リズムアート教室ありんこ」では、子ども一人ひとりの特性に寄り添う“療育リトミック”を行っています。
音やリズムを通じて自然にからだを動かし、バランス感覚や協調性を育みながら、遊びの中で「できた!」を積み重ねていくレッスンです。
コース紹介
自宅出張レッスン
入退院をくり返し、
なかなか外出できないお子さんや、医療ケアが必要だったり、肢体的不自由のあるお子さんにも音楽的な刺激を与え、自宅でママとたくさんスキンシップをとることが出来ます。
教具教材を使用するのはもちろん、発育や話し相手としても大変ご満足いただいております。
(別途交通費要)
個別プログラム(2歳〜4歳)
個別プログラム【~年中まで】(50分レッスン)
個別プログラムレッスンは、お母さんとの事前の聞き取り(体調面や情緒面はもちろん、園での様子、家での様子、コミュニケーション方法など)をおこない、力をつけていきたいの方向性を一緒に決めていきます。
ダウン症児(療育センター通園)
R君の場合
個別プログラム開始当初…
言葉はまだしっかり出ないものの、落ち着いていて好奇心が旺盛だったので、 お母さんとスキンシップを取りながら、
どんな活動が好きなのか苦手なのかをゆっくり見守っていくことにしました。
🔶リトミック
リトミックが与える集中力や即時反応力で、身体の動かし方やバランス感覚を養う。
歩く、走る、ユラユラ、すわる、跳ぶ、強弱、大小、速遅、等速リズムなど
手指活動、腕の使い方、手首の発達、グーパー、指の使い方(モノを掴み方、5本指でor3本指で)、(モノのつまみ方、2本指で)を獲得するために、モンテッソーリ教具を使って練習中。
🔶ビジョントレーニング 毎回必ず10分ほど。
(子どもの場合、一日15分と言われています)
スカーフキャッチ、ボールキャッチ、読み聞かせ絵本 ほかにも
【音楽的要素】 ハンドベル、木琴、たいこ(大きさ3種類)、ウッドブロック
【PT風ボディイメージ】ジャンプ、フープくぐり、けんけんぱ、不安定感
【図工的要素】 ありんこ工作、色と形(同じ色⇔ちがう色)、おりがみ
【ワーキングメモリ】 カードを使って短期記憶をする活動
【OT風 作業的要素】 モンテッソーリ教具を使用
【ST風 言語的要素】 もの、どうぶつ、くだもの、やさいなどの名前や色、形を知る
個別プログラム(5歳〜)
個別プログラム【年長~】(50分レッスン)
自閉症児(特別支援学校1年)A君の場合
個別プログラム開始当初…
🔶ひらがな、カタカナが読めたので、毎回ホワイトボードで活動を一緒に読み上げる。(活動に時間設定を設けるためにタイマーを用意したが、すんなり終わらせることができたので、その日以降は使わないことに)
※この時点で学校で取り組んでいた学習内容は、うんぴつ、ひらがな、漢字(一~十)すうじ(たし算引き算、1~50ぐらいまで)、〇△□のマッチング など。
その後、お母さんとの話し合いで、学校では取り組まない学習をレッスンでおこなうことに。
追加された内容は
🔶マッチング(ことばのカテゴリ分け)や分類(カードと同じ色と文字を合わせる)など。
🔶ローマ字を覚えてパソコンのタッチにつなげていく
(アルファベット⇒ローマ字⇒キーボード打ち)
ほかにも
【MT的要素】 ハンドベル、木琴、右手と左手をバラバラに動かす、指番号(ピアノレッスンのような)
【図工的要素】 ありんこ工作、おりがみ
【生活的要素】 せんたくものを干す、たたむ、雑巾しぼり
【OT的要素】 モンテッソーリ教具を使用
【ST的要素】 感情と気持ち(どんなかお?どんな気持ち?)はんたいことば、オノマトペ、ものの名前
療育リトミックについて
リズムアート教室ありんこ独自の
療育リトミックについて
いろいろな特性を持った子どもたちに
必要なリトミックレッスンとはなんだろう?
本来、習い事としてリトミック教室に通う場合、
鍵盤楽器を弾けるようになってほしい導入としての
レッスン内容になっていることが多いと思われます。
(健常児向けレッスン)
誰もが無意識のうちにできる何気ない運動でも、
それをスムーズに正確にこなすには、
目で空間的な位置を確認し、
自分の身体と対象との距離を測ったり、
目と手足を連動して動かしたり、
体のバランスを取ったり、
あるいは力の入れ具合を調節したり、
動くタイミングをはかったりといった
さまざまなレベルの情報を統合して運動に結びつけなくてはなりません。
その力を引き出すために、
季節感のある道具を用いたり、
ちょっとしたゲーム性のある活動に
することによって、
「学ばされている感」をできるだけなくす必要性があると考えます。
子ども一人ひとりの人格・才能・創造力・精神的や
身体的な能力の発達を
それぞれ考慮しながら、指導したり、
言葉かけをすることによって、
その特性を生かせるはずです。
リトミックレッスンを
積み重ねていくことによって、からだの中にリズム感が刻み込まれす。
「階段をのぼる」「歯をみがく」「自転車をこぐ」など生活の中には
たくさんのリズムがあり、
これらは楽器を演奏するよりも、
とても身近で大切なものだと思います。
障がいのある子にリトミックが良い理由
発達障がいが原因で、言葉や指示をうまく聞き取ることができない子どもでも、
音楽は人間の脳に 直接的に働きかけるものですから自ら進んで聞いてくれるでしょう。
また、リトミックに失敗の概念は存在しません。
正解があるような物事の場合、失敗することがひどくストレスになってしまったり、
やる前に失敗した時のことを考えて躊躇してしまったりすることも多いでしょう。
音楽はありのままで良いのだと教えてくれる存在です。
自らを解放し、楽しく体を動かした後の子どもはとても清々しい表情をしているものです。
さらに集団でリトミックをすることによって、模倣が苦手な発達障がいの
子どもの模倣能力を育てることもできます。
子どもは人の動きや言葉を聞いて、それをマネしながら成長していきます。
リトミックは自分が思うとおりに動きますが、
他の人の動きを見て心が動けば自分も同じことをやってみたいと思うはずです。
まずは体験レッスンからどうぞ↓↓↓